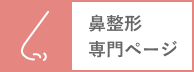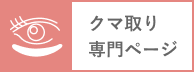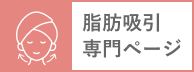鼻整形で呼吸がしづらい?術後の原因と改善法を徹底解説

鼻整形を受けた後、「呼吸がしづらい」と感じる方は少なくありません。美しい鼻のラインを手に入れたはずなのに、日常生活に支障が出てしまうと不安になりますよね。
実は、術後の呼吸困難は一時的なものから、構造的な問題まで、さまざまな原因が考えられます。多くの場合、適切な対処によって改善が可能ですが、放置すると生活の質(QOL)に大きな影響を与えることもあります。
この記事では、形成外科・美容外科の専門医として、鼻整形後に呼吸がしづらくなる原因とその改善法について、詳しく解説していきます。
鼻整形後に呼吸がしづらくなる主な原因
鼻整形後の呼吸困難には、いくつかの典型的な原因があります。まず理解していただきたいのは、鼻は「美しさ」と「機能」の両方を担う器官だということです。
術後の腫れと粘膜の浮腫
手術直後から数週間は、鼻の内部が腫れることで空気の通り道が狭くなります。これは手術による自然な反応です。粘膜の浮腫(むくみ)によって鼻腔が一時的に狭まり、呼吸がしづらく感じられます。
特に鼻中隔延長や鼻尖形成などで粘膜を剥離した場合、術後1〜2週間は粘膜が浮腫を起こしやすくなります。この浮腫によって鼻腔が一時的に狭くなり、空気の流れが変わってしまうのです。
鼻中隔の変形や弯曲
鼻中隔は、2つの鼻の穴の間にある仕切りのことです。手術の際に鼻中隔に負担がかかったり、術後の治癒過程で変形したりすることがあります。
鼻中隔が大きく弯曲していると、鼻腔の通気が悪くなります。曲がって出っ張った部分の粘膜が引き延ばされて薄くなるため、粘膜にもトラブルが起こりやすくなります。成人の多くは左右どちらかに鼻中隔が曲がっていますが、手術によってその弯曲が悪化することもあるのです。
プロテーゼや軟骨移植による圧迫
鼻筋を高くするために挿入したプロテーゼや、鼻先を整えるために移植した軟骨が、鼻腔を圧迫することがあります。特に、適切なサイズや位置でない場合、呼吸の妨げになることがあります。
高すぎるプロテーゼが動いたり、極度な垂れ鼻となってしまったりすると、鼻先が凹んで見えてしまうだけでなく、呼吸にも影響を及ぼします。
内部バルブ(Internal Valve)の狭窄
鼻の内部には「内部バルブ」と呼ばれる、空気の流れを調整する部分があります。手術によってこの部分が狭くなると、呼吸時に抵抗を感じやすくなります。
鼻背軟骨の変形がある場合、この内部バルブの開存が損なわれ、安定した鼻の通りが確保できなくなることがあります。
術後の時期別・呼吸困難の特徴
術後1週間まで:急性期の腫れ
手術直後から1週間は、最も腫れが強い時期です。鼻の中にガーゼが入っている場合もあり、ほとんど鼻呼吸ができない状態になることもあります。
この時期は口呼吸が中心になりますが、これは一時的なものです。術後2日目に鼻の中のガーゼを取ると、少しずつ呼吸が楽になっていきます。
術後2週間〜1ヶ月:粘膜の回復期
腫れは徐々に引いていきますが、粘膜の回復には時間がかかります。この時期は、鼻の中が乾燥しやすく、分泌物も増加しやすいため、不快感を抱えることが少なくありません。
術後3週目以降は大分、外の腫れと鼻の中の腫れがとれてきます。鼻の形も鼻の通りも大きく改善していくことが期待できます。
術後3ヶ月以降:最終的な評価期
術後3ヶ月を過ぎても呼吸困難が続く場合は、構造的な問題がある可能性があります。この段階で改善が見られない場合は、医師に相談することが重要です。
ほぼ腫れも落ち着き、鼻の形も鼻の通りも最終的な状態に近づいていきます。

呼吸困難を改善するための対処法
術後すぐにできるセルフケア
術後の呼吸困難を少しでも和らげるために、自宅でできるケアがあります。まず大切なのは、鼻の中を適切に保湿することです。
ワセリンやヒアルロン酸入りジェルなどを赤ちゃん用綿棒に少量取り、鼻腔の入り口(1cm以内)に優しく塗布します。これにより乾燥によるムズムズが軽減されます。
市販されている0.9%生理食塩水の鼻腔用スプレーは、刺激が少なく粘膜の保湿と洗浄に有効です。朝晩の2回を目安に使うことで、鼻の中が清潔に保たれ、ムズムズが和らぐことがあります。
医療機関での専門的治療
セルフケアで改善しない場合や、症状が強い場合は、医療機関での治療が必要です。術後2〜3日以降、医師の判断でクリニック内での鼻洗浄処置(生理食塩水による洗い流しや微小吸引)を行う場合があります。
鼻中隔の弯曲が原因の場合、「鼻中隔矯正術」という手術が必要になることもあります。曲がった軟骨を手術でまっすぐにすることで、症状を改善します。
プロテーゼや軟骨の調整・再手術
プロテーゼや移植軟骨が原因で呼吸困難が起きている場合、それらの位置調整や入れ替えが必要になることがあります。
適切なプロテーゼに入れ替え、綺麗な鼻筋にしつつ、自然な高さを形成することで、呼吸機能も改善できます。鼻中隔軟骨を移植して延長したり、変形矯正のみならず内部バルブの開存を図ったりすることで、安定した鼻の通りを確保できます。
鼻閉に対する保存的治療
アレルギー性鼻炎などが合併している場合は、点鼻薬や内服薬による治療も有効です。鼻中隔が弯曲していてもともと狭い鼻腔が、アレルギー性鼻炎による粘膜の腫れでさらに狭まってしまうため、鼻汁、鼻詰まりといった症状が悪化しやすくなります。
鼻腔が狭く、よく鼻詰まりを起こすと、鼻腔の通気性が失われて細菌が繁殖しやすい環境になります。その結果、粘膜が炎症を起こしやすくなり、炎症を繰り返すことで慢性副鼻腔炎の原因につながることもあります。
呼吸困難を防ぐための術前の注意点
医師との十分なカウンセリング
手術前に、医師と十分にコミュニケーションを取ることが最も重要です。希望する鼻の形だけでなく、現在の鼻の状態や呼吸機能についても詳しく相談しましょう。
鼻整形は「医療行為」です。医師による適切な診断のもと、適切に、適正な価格で行われるべきだという信念のもと、患者様ファーストで診療を行うことが大切です。
鼻の機能を考慮した手術計画
美しさだけでなく、呼吸機能も考慮した手術計画が必要です。鼻中隔の状態や鼻腔の広さなど、機能面も含めた総合的な評価が重要になります。
オープンアプローチで手術を行う場合、鼻背軟骨や鼻中隔軟骨などの軟部組織成分の変形をしっかり見ながらいい形にすることが大変重要です。
既往症の申告
アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎など、鼻に関する既往症がある場合は、必ず医師に伝えましょう。これらの疾患がある場合、術後の呼吸困難のリスクが高まることがあります。
鼻中隔弯曲症がある場合も、事前に治療しておくことで、術後の呼吸機能を良好に保つことができます。

呼吸困難が続く場合のリスクと対処
生活の質(QOL)への影響
鼻は呼吸という生存に欠かせない基本となる機能を担う器官です。そのため鼻に症状を抱えているとQOL(クオリティ・オブ・ライフ/生活の質)が著しく下がり、本来持っている能力や才能を活かしきれなくなってしまうケースも出てきます。
鼻中隔弯曲症で鼻呼吸ができず口呼吸を繰り返すようになると、呼吸が浅くなって脳が必要とする酸素が不足し、しつこい頭痛や、吐き気を伴う片頭痛といった症状が現れることがあります。
睡眠時無呼吸症候群のリスク
鼻呼吸が困難な状態が続くと、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。下あご全体が小さい方は、口が閉じにくいので口を閉じるために無意識に下あごが入っています。
下あご全体がかなり小さな場合は、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸障害も合併してきますので、しっかりとした診断と治療計画が必要となります。
慢性副鼻腔炎のリスク
鼻腔が狭く、よく鼻詰まりを起こすと、鼻腔の通気性が失われて細菌が繁殖しやすい環境になります。その結果、粘膜が炎症を起こしやすくなり、炎症を繰り返すことで慢性副鼻腔炎の原因につながります。
頭痛や分泌物の増加など、慢性副鼻腔炎の症状が現れ出したら注意が必要です。
早期の医師への相談が重要
術後3ヶ月を過ぎても呼吸困難が続く場合や、日常生活に支障が出ている場合は、早めに医師に相談しましょう。放置すると、さらに状態が悪化する可能性があります。
術後の不安に対応する24時間無料相談窓口を設けているクリニックもあります。小さなことでも構いません。すこしでも不安なことはお気軽に相談してください。
まとめ
鼻整形後の呼吸困難は、多くの場合、術後の一時的な腫れや粘膜の浮腫が原因です。適切なケアと時間の経過によって改善することがほとんどです。
しかし、鼻中隔の変形やプロテーゼの位置不良など、構造的な問題が原因の場合は、専門的な治療が必要になります。術後3ヶ月を過ぎても症状が続く場合は、必ず医師に相談しましょう。
鼻整形は、美しさと機能の両方を考慮した治療が重要です。手術前に医師と十分にコミュニケーションを取り、美容面だけでなく呼吸機能も含めた総合的な治療計画を立てることが、満足のいく結果につながります。
当クリニックでは、「正確な診断の下、適切な術式を、適正価格で患者様にご提案する」を信念に日々診療を行っています。鼻整形に関するご相談は、最初から医師によるカウンセリングを行っていますので、お気軽にご相談ください。
詳細はこちら:東京美専クリニック
情報
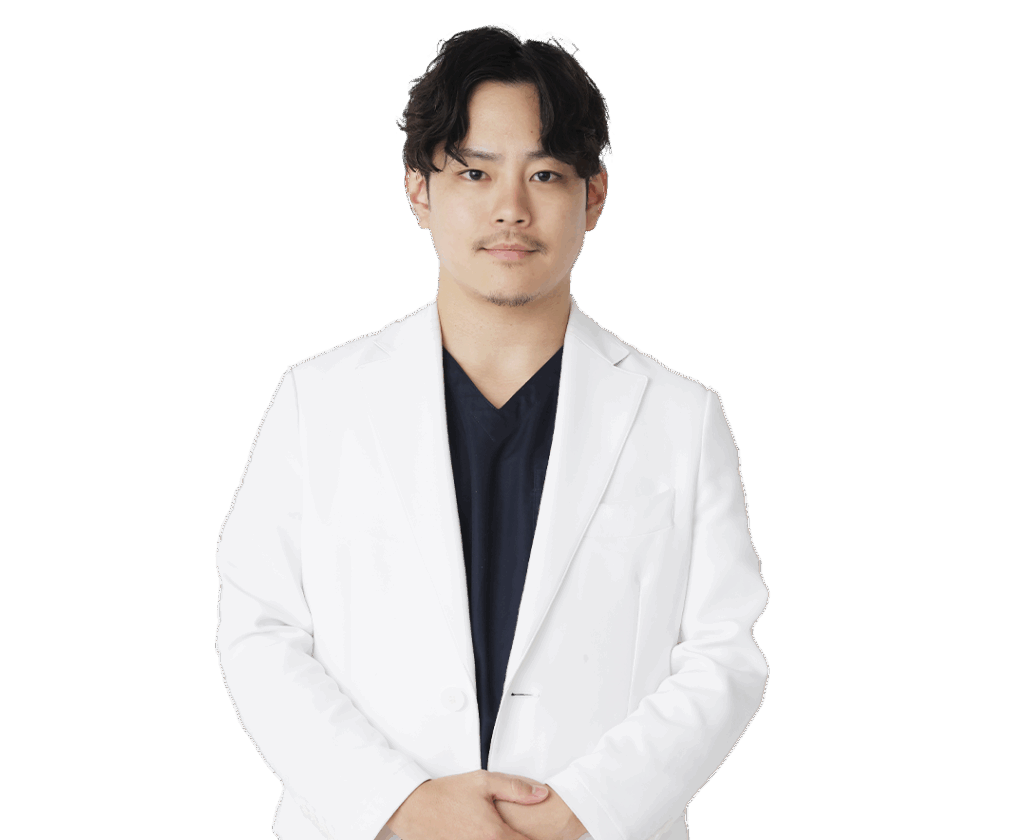
東京美専クリニック院長 土田諒平
経歴
大分県出身
京都大学工学部物理工学科 卒業
奈良県立医科大学医学部 卒業
ハーバード大学医学部Joslin Diabetes Center 留学
奈良県立医科大学附属病院 勤務
近畿大学奈良病院 勤務
天理よろず相談所病院 勤務
東京美専クリニック 開業
東京大学医学部卒業後、大学附属病院にて形成外科・美容外科の臨床経験を積む。
その後、大手美容クリニックにて年間1,000件以上の施術を担当。
顔面のバランス分析や自然な仕上がりに定評があり、「美しさと調和」の美容医療を提案し続けている。
現在は東京・表参道にある東京美専クリニックにて、院長として診療・施術・カウンセリングを担当。
鼻整形、目元整形、輪郭形成、注入治療などを得意とし、幅広い年代の患者様に対応している。
本記事は、美容外科の現場で多くの施術・カウンセリングを行ってきた経験をもとに執筆しています。
インターネット上の不確かな情報ではなく、医学的知見・現場での実績に基づく情報提供を心がけています。
美容医療に不安を抱える方にもわかりやすく、正確な情報を届けられるよう努めています。
「美容整形は“変える”のではなく、“調和させる”もの」
あなたが本来持っている魅力を最大限に引き出すために、医学的知識と審美眼をもってサポートします。