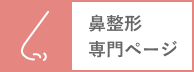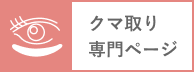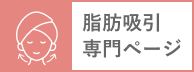鼻整形の失敗例と修正術|美容外科医が教える正しい知識
鼻は顔の中心に位置し、顔全体の印象を大きく左右する重要なパーツです。そのため、鼻整形は美容外科の中でも人気の高い施術となっています。しかし、鼻整形は繊細な技術を要するため、失敗例も少なくありません。
鼻整形で失敗してしまうと、日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的な負担も大きくなります。「思っていた仕上がりと違う」「不自然な見た目になってしまった」など、後悔の声も少なくないのです。
私は美容外科医として多くの鼻整形症例を手がけてきました。その経験から、失敗例とその修正方法について詳しくお伝えします。これから鼻整形を検討している方はもちろん、すでに施術を受けて結果に満足していない方にも役立つ情報をご提供します。
鼻整形が不自然になる原因とは?
鼻整形後に「不自然だ」と感じる原因はいくつかあります。まず最も多いのが、顔全体とのバランスが取れていないケースです。
鼻は顔の中心に位置するため、他のパーツとの調和が非常に重要です。どんなに技術的に優れた施術でも、患者さんの顔全体のバランスを考慮せずに行うと、不自然な印象を与えてしまいます。
例えば、小さな顔に対して鼻筋を高くしすぎると、不釣り合いな印象になります。また、横顔のバランスも重要で、鼻先の角度が不自然だと、全体の印象が大きく変わってしまうのです。
次に多いのが、使用する素材や技術の問題です。プロテーゼの選択ミスや挿入位置の誤り、ヒアルロン酸の過剰注入などが原因で、不自然な仕上がりになることがあります。
鼻筋が高すぎる問題
鼻筋を高くする施術は、プロテーゼを使用することが一般的です。しかし、高すぎる鼻筋は不自然に見えるだけでなく、日本人の顔立ちに合わないことが多いです。
日本人を含むアジア人の鼻は、欧米人と比較して低い傾向にあります。そのため、欧米人のような高い鼻筋を目指すと、かえって違和感が生じてしまうのです。
また、プロテーゼを挿入する際に、骨膜下ではなく骨膜上に挿入してしまうと、時間の経過とともに皮膚が薄くなり、プロテーゼが透けて見えるようになることもあります。白いプロテーゼが透けると、鼻が白っぽく見え、不自然さが増します。
鼻先の形状の問題
鼻先の形状も、不自然さを感じる大きな要因です。鼻先が尖りすぎていたり、逆に丸すぎたりすると、正面からは気にならなくても、横顔や下から見上げたときに違和感が出ることがあります。
特に鼻尖形成や鼻中隔延長といった術式は、もともと欧米の「高く大きい鼻」を対象に開発されたものです。アジア人は軟骨が小さく皮膚が厚いため、欧米の技法をそのまま適用すると「鳥のくちばし様変形」などの不自然な変形が起きやすくなります。
鼻整形でよくある失敗例
鼻整形の失敗例は多岐にわたります。ここでは、実際によく見られる失敗例をいくつか紹介します。
プロテーゼによる失敗
プロテーゼを使用した鼻整形では、以下のような失敗例が見られます。
まず挙げられるのが、プロテーゼの位置ずれです。プロテーゼが本来あるべき位置からずれると、鼻筋が曲がって見えたり、不自然な膨らみが生じたりします。これは、プロテーゼを挿入するスペースの確保が不十分だったり、固定が不適切だったりすることが原因です。
また、プロテーゼの透けも大きな問題です。プロテーゼが骨膜上に挿入されると、時間の経過とともに皮膚が薄くなり、プロテーゼが透けて見えるようになります。これにより、鼻が白っぽく見えたり、エッジが目立ったりして不自然な印象を与えます。
さらに深刻なのが、プロテーゼによる感染です。プロテーゼ挿入時に細菌が入り込むと、炎症を起こし、最悪の場合は皮膚の壊死を引き起こすことがあります。これは医師の技術不足や、クリニックの衛生管理の問題が原因となることが多いです。
ヒアルロン酸注入による失敗
ヒアルロン酸注入は、メスを使わない手軽な施術として人気がありますが、以下のような失敗例が見られます。
まず、過剰注入による不自然さです。ヒアルロン酸を注入しすぎると、鼻が膨らんで不自然な印象になります。特に鼻筋や鼻先に過剰に注入すると、バランスが崩れた印象になりがちです。
また、注入後にしこりができることもあります。これは、ヒアルロン酸が均一に広がらず、一部に固まってしまうことで起こります。触るとブヨブヨした感触があり、外から見てもデコボコして見えることがあります。
失敗を修正しようと何度も注入を繰り返すと、さらに不自然になることがあるため注意が必要です。ヒアルロン酸は時間とともに吸収されるため、一時的な対処法として考えるべきでしょう。
鼻中隔延長術の失敗
鼻中隔延長術は、鼻先を高くしたり、上向きの鼻を改善したりする施術ですが、以下のような失敗例があります。
最も多いのが、時間の経過とともに鼻先が沈み込んでしまうケースです。はじめは整った鼻先だったものの、感染や拘縮、移植軟骨のズレなどにより、1年以内に沈み込みが始まり、数年後には明らかに高さが失われることがあります。
また、軟骨の支持力が不足していると、上に乗せた耳介軟骨の重みに耐えきれず、沈み込みや変形が起こることもあります。これは「座布団現象」と呼ばれ、柔らかい土台に耳介軟骨を乗せると、座布団のように沈み込み、本来出したかった高さが得られないという問題です。
さらに、十分な長さや強度がない耳介軟骨で鼻中隔延長を行うと、時間の経過とともに軟骨が崩れてしまい、鼻先が再び落ち込む現象が起こる可能性があります。
鼻整形の修正術とは
鼻整形の失敗を修正するには、様々な方法があります。ここでは、主な修正術について説明します。
プロテーゼ修正
プロテーゼによる失敗を修正する場合、まずは既存のプロテーゼを除去する必要があります。その後、患者さんの顔のバランスに合わせて新しいプロテーゼを選択し、適切な位置に挿入します。
プロテーゼが透けて見える場合は、自家組織(脂肪や筋膜など)を移植して厚みを出すことで改善できることもあります。また、感染が起きている場合は、まず感染を治療してから修正手術を行います。
私の経験では、プロテーゼの修正は比較的成功率が高い施術です。ただし、何度も修正を繰り返すと、組織が傷つき、さらに修正が難しくなることもあるため、信頼できる医師による適切な修正が重要です。
ヒアルロン酸の溶解と再注入
ヒアルロン酸による失敗を修正する場合、ヒアルロニダーゼという酵素を注射してヒアルロン酸を溶解することができます。その後、必要に応じて適量のヒアルロン酸を再注入します。
しこりができている場合は、マッサージで改善することもありますが、効果がない場合はヒアルロニダーゼで溶解するのが確実です。ただし、ヒアルロニダーゼは周囲の天然のヒアルロン酸も溶解する可能性があるため、専門医による適切な処置が必要です。
ヒアルロン酸は時間とともに自然に吸収されるため、何もしなくても1〜2年程度で元に戻ることが多いです。しかし、不自然さが気になる場合は、早めに専門医に相談することをお勧めします。
鼻中隔延長術の修正
鼻中隔延長術の失敗を修正する場合、まずは現状の問題点を正確に診断することが重要です。沈み込みが起きている場合は、より強固な支持構造を作るために、耳介軟骨や肋軟骨などを使用して再建します。
特に、鼻中隔延長の修正は難易度が高く、経験豊富な医師による施術が必要です。修正手術では、既存の軟骨の状態や瘢痕の問題など、様々な要素を考慮する必要があります。
完全に元通りにするのは困難ですが、「自分らしい自然な鼻」に近づける修正手術は可能です。必要に応じて、鼻先の軟骨(大鼻翼軟骨)を自然な形に再配置したり、軟部組織(脂肪や皮下組織)を補いボリューム調整したり、鼻中隔の構造補強を行ったりします。
鼻整形の失敗を防ぐポイント
鼻整形の失敗を防ぐためには、以下のポイントに注意することが重要です。
信頼できる医師の選択
鼻整形の成功には、医師の技術と経験が非常に重要です。信頼できる医師を選ぶためには、以下の点をチェックしましょう。
まず、医師の経歴や実績を確認しましょう。形成外科や美容外科の専門医資格を持っているか、鼻整形の症例数が豊富かなどが重要な指標となります。また、実際の症例写真を見せてもらい、自分の理想に近い仕上がりを実現できるかどうかを確認することも大切です。
さらに、医師が患者の希望をしっかり聞き、適切なアドバイスをしてくれるかどうかも重要です。「それは難しい」「そのデザインは不自然になる可能性がある」など、率直に伝えてくれる医師は信頼できると言えるでしょう。
私自身も患者さんには常に正直にアドバイスするよう心がけています。時には希望通りにできないこともありますが、それを伝えることで、後々の失敗や後悔を防ぐことができるのです。
適切な施術方法の選択
自分の希望や顔の特徴に合った施術方法を選ぶことも重要です。例えば、鼻筋を高くしたい場合でも、プロテーゼ、ヒアルロン酸、自家組織移植など、様々な方法があります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、医師としっかり相談し、自分に最適な方法を選びましょう。例えば、ヒアルロン酸は手軽ですが持続期間が短く、プロテーゼは長期的な効果がありますが異物反応のリスクがあります。
また、複数の施術を組み合わせることで、より自然な仕上がりになることもあります。例えば、プロテーゼで鼻筋を高くしつつ、小鼻縮小術で全体のバランスを整えるといった方法です。
リスクと限界の理解
どんな手術にもリスクはつきものです。鼻整形のリスクとしては、感染、出血、腫れ、内出血、左右差、瘢痕形成などがあります。これらのリスクを理解した上で、施術を受けるかどうかを判断することが大切です。
また、施術には限界もあります。例えば、皮膚の厚さや軟骨の状態によっては、希望通りの形にできないこともあります。医師から説明されたリスクや限界をしっかり理解し、現実的な期待を持つことが、満足度の高い結果につながります。
私のクリニックでは、カウンセリングの際に必ずリスクと限界について詳しく説明し、患者さんの理解を得るようにしています。これにより、術後の満足度が高まるだけでなく、トラブルの発生も減少しています。
鼻整形修正の実例
ここでは、実際に行われた鼻整形の修正例をいくつか紹介します。
プロテーゼ修正の症例
40代女性の症例です。20年前に挿入したプロテーゼがずれて鼻筋が曲がり、プロテーゼの先端が鼻の穴から飛び出して感染していました。
まず抗生剤で感染をある程度コントロールしてから、古いプロテーゼを除去し、適切なサイズと形状の新しいプロテーゼに入れ替えました。同時に鼻先の整形も行い、鼻筋をまっすぐに修正するとともに、鼻先の丸みや高さも改善しました。
術後は感染も収まり、自然な鼻のラインを取り戻すことができました。患者さんからは「長年の悩みが解消された」と喜びの声をいただきました。
鼻中隔延長術の修正症例
30代女性の症例です。他院で鼻中隔延長術を受けましたが、術後1年ほどで鼻先が徐々に沈み込み、上向きの鼻に戻ってしまいました。
診察の結果、使用された耳介軟骨の支持力が不足していることが判明しました。そこで、より強固な肋軟骨を使用して鼻中隔を再延長し、しっかりとした支持構造を構築しました。
術後は鼻先の位置が安定し、自然な形状を維持できるようになりました。この症例からも、鼻中隔延長術には適切な素材選択と技術が重要であることがわかります。
小鼻縮小術の修正症例
20代女性の症例です。他院で小鼻縮小術を受けましたが、傷跡が目立ち、鼻翼の形も左右非対称になってしまいました。
修正手術では、まず既存の瘢痕を丁寧に切除し、鼻翼の形を整えました。さらに、鼻孔縁の形も調整し、自然な小鼻の形状を再現しました。
術後は傷跡も目立たなくなり、左右対称の自然な小鼻を実現することができました。小鼻縮小術は比較的シンプルな手術に見えますが、繊細な技術を要する施術であり、経験豊富な医師による施術が重要です。
鼻整形修正のアフターケア
鼻整形の修正術後は、適切なアフターケアが重要です。ここでは、修正術後のケアについて説明します。
腫れと内出血の管理
修正術後は、腫れや内出血が生じることがあります。これらは通常、時間とともに自然に改善しますが、以下の方法で管理することができます。
腫れを軽減するには、術後48時間は氷嚢などで冷やし、頭を高くして寝ることが効果的です。また、医師の指示に従って消炎鎮痛剤を服用することも重要です。内出血は通常1〜2週間で消失しますが、気になる場合は化粧でカバーすることもできます。
腫れが完全に引くまでには数か月かかることもありますので、焦らず経過を見守ることが大切です。特に修正術の場合は、通常の整形術よりも腫れが長引くことがあります。
感染予防と傷跡ケア
感染を予防するためには、医師の指示に従って抗生物質を服用し、傷口を清潔に保つことが重要です。シャワーや洗顔の際は、傷口に直接水がかからないよう注意しましょう。
傷跡のケアとしては、医師の指示に従ってシリコンテープや傷跡用クリームを使用することが効果的です。また、日焼けは傷跡を目立たせる原因となるため、外出時は日焼け止めを塗るか、帽子などで日差しを避けることをお勧めします。
私のクリニックでは、術後の傷跡ケアについて詳しく説明し、必要に応じて専用のケア製品も提供しています。適切なケアにより、傷跡は徐々に目立たなくなっていきます。
定期的な経過観察
修正術後は、定期的に医師の診察を受けることが重要です。術後の経過を医師が確認することで、問題があれば早期に対処することができます。
また、何か気になる症状があれば、すぐに医師に相談することをお勧めします。「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断せず、専門家の意見を求めることが、良好な結果につながります。
東京美専クリニックでは、術後の不安に対応するため、24時間無料の相談窓口を設けています。小さなことでも気軽に相談できる環境を整えることで、患者さんの安心と満足度の向上に努めています。
まとめ
鼻整形は顔の印象を大きく変える効果的な施術ですが、失敗のリスクも伴います。本記事では、鼻整形の失敗例とその修正方法について詳しく解説しました。
失敗を防ぐためには、信頼できる医師を選び、自分に適した施術方法を選択すること、そしてリスクと限界を理解することが重要です。また、すでに失敗を経験している方には、適切な修正術によって改善できる可能性があることをお伝えしました。
鼻整形の修正は通常の整形よりも難しく、高度な技術を要します。そのため、修正を検討する際は、修正手術の経験が豊富な医師を選ぶことが特に重要です。
私たち東京美専クリニックでは、患者さん一人ひとりの悩みに寄り添い、最適な治療法をご提案しています。鼻整形の失敗でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な医師による適切な診断と治療で、自然で美しい鼻を取り戻すお手伝いをいたします。美容整形は「医療行為」です。医師による適切な診断のもと、適切に、適正な価格で行われるべきだという信念のもと、患者様ファーストで日々診療を行なっています。鼻のお悩みがございましたら、ぜひ 東京美専クリニック にご相談ください。
著者情報
東京美専クリニック院長 土田諒平
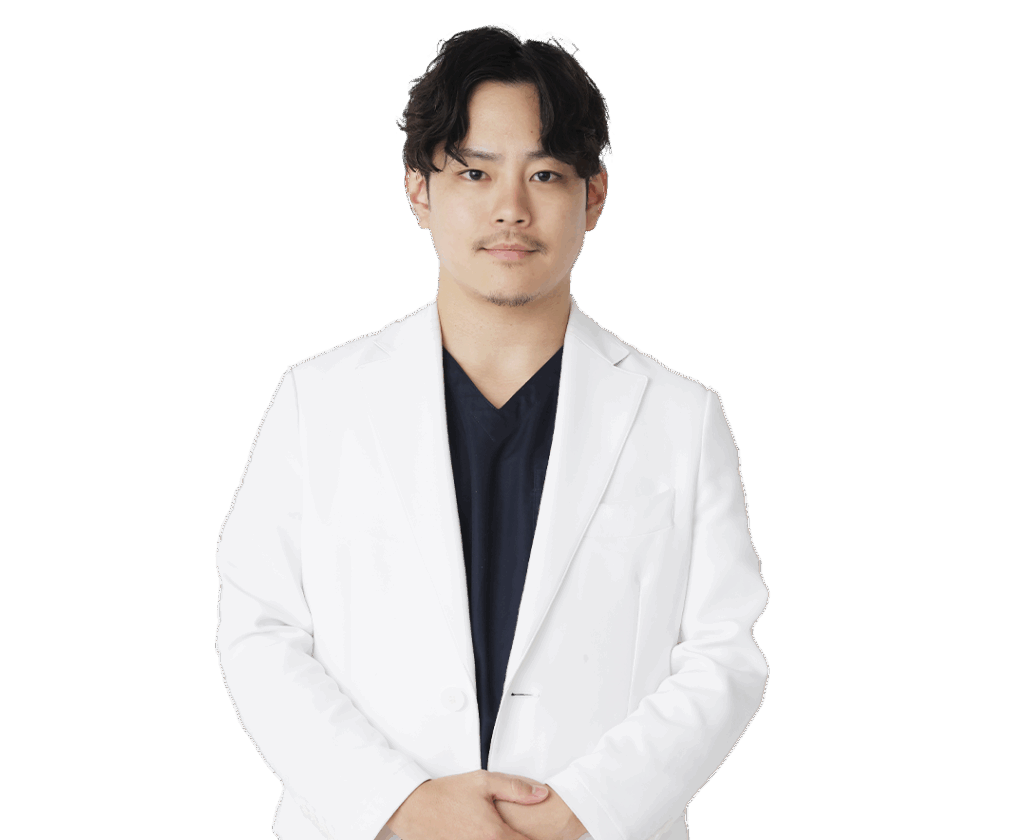
経歴
- 大分県出身
- 京都大学工学部物理工学科 卒業
- 奈良県立医科大学医学部 卒業
- ハーバード大学医学部Joslin Diabetes Center 留学
- 奈良県立医科大学附属病院 勤務
- 近畿大学奈良病院 勤務
- 天理よろず相談所病院 勤務
- 東京美専クリニック 開業